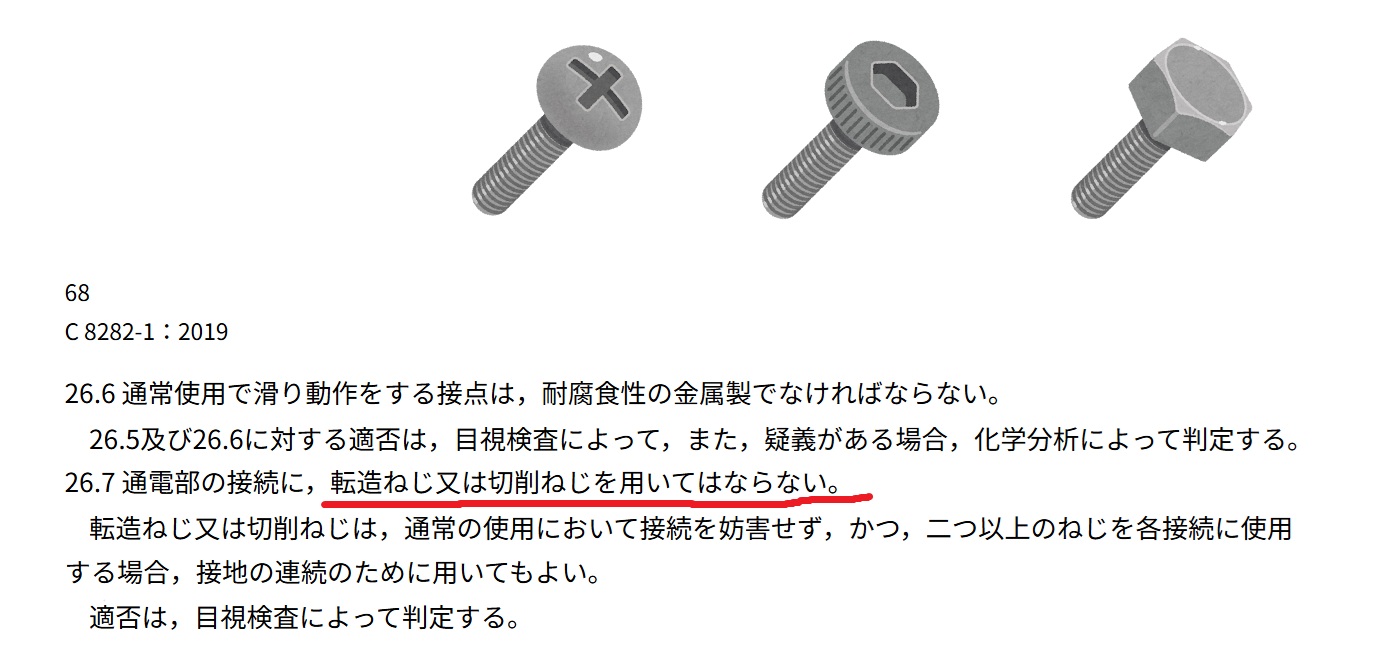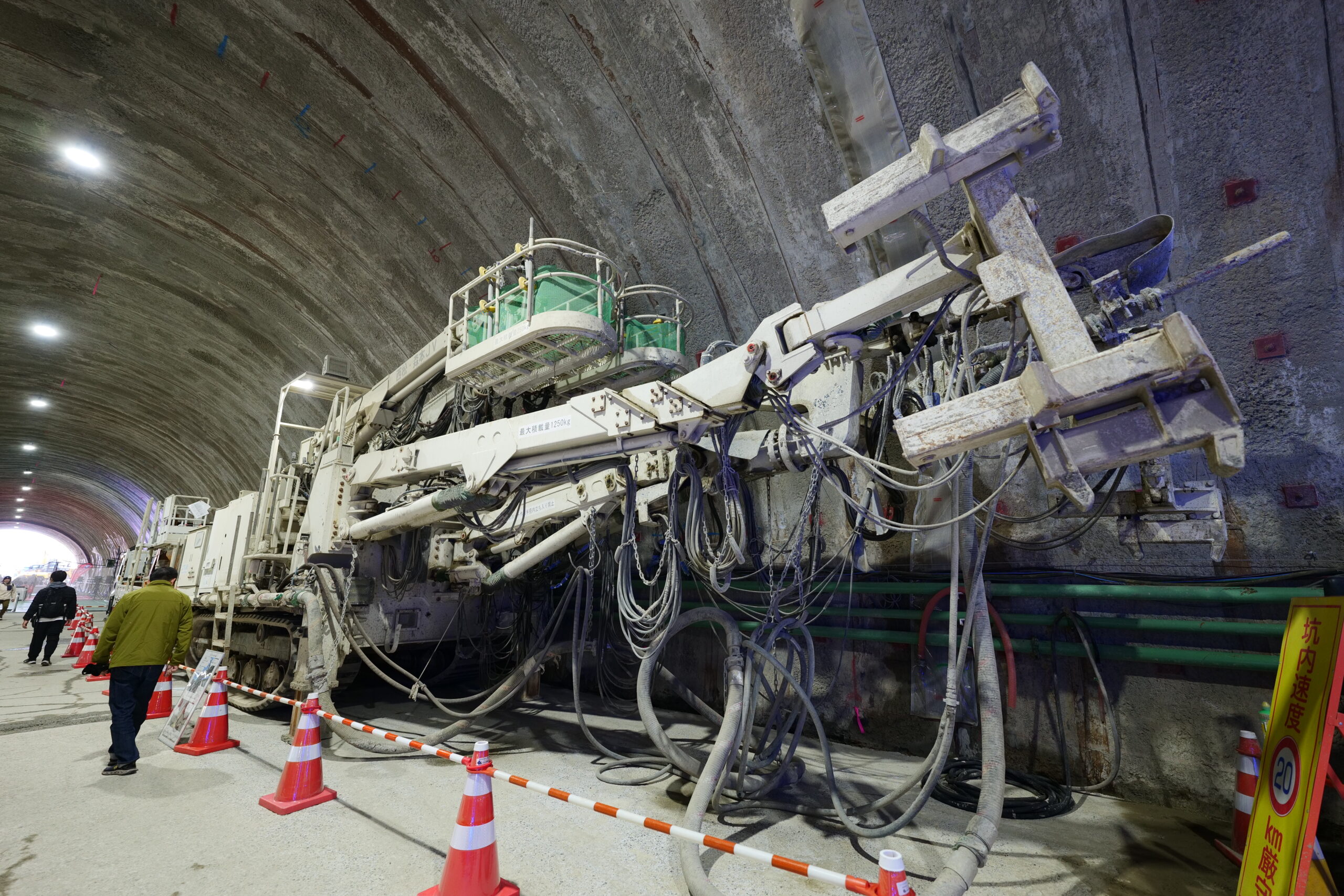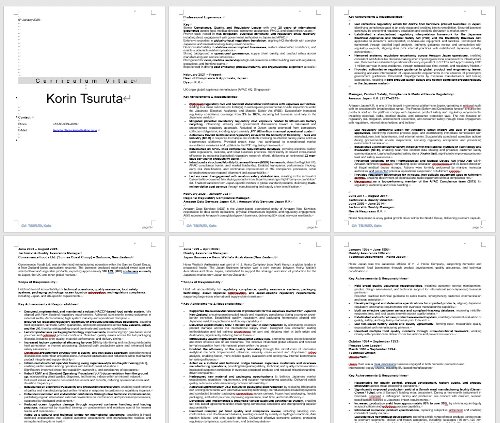通電部の接続に、転造ネジまたは切削ネジを用いてはならない
JIS C 8282-1のJapan Deviationの翻訳をしていたら。
通電部の接続に、転造ネジまたは切削ネジを用いてはならない
という行があって、え?なんで? と思って調べてみました。
そもそもネジの作り方には色々ありまして、
転造ネジ:金属棒をギザギザでぎゅっと抑え込んで変形させてネジを刻む方法です。 モノタロウの解説が良い。
切削ネジ:金属棒を削ってネジ山を作る中世以来の方法。 ミスミさんの解説はこちら
どちらも精度が出ないのでネジ山が線接触になりやすく電気回路のように常に温まったり冷えたりする場所に使用すると緩みやすく、不適当(緩むとそこが発熱する)。
ただ、ネジの製造法はほぼ転造か切削らしいので、となると、配電盤に付いているあれらのネジは何?
冷間圧延? 転造より遥かに大きな圧力をかけて表面を平滑に作れるのが冷間圧延ネジらしい。 ボサードさんの説明
電気配線用のネジは「あったもんを使う」わけには行かないのねぇ。 どおりで圧着端子や噛み込み端子が人気なわけです。 ネジなんで一般住宅の配線ではほぼブレーカーにしか使わんね そういえば。
(我が家の配電盤は古いのでネジだらけです)
へー! 勉強になった。
Share this content: